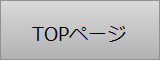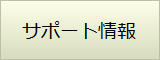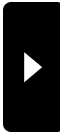2016年10月31日
耐パンクタイヤ
自転車のトラブルで一番多いのと、一番困るのがパンクかと思います。
特に見知らぬ出先でパンクした時は途方に暮れてしまいますね。
パンクの原因は様々ありますがその中で突き刺しパンクに強い
ブリヂストンの上位モデルの通学車に装備されているプラス(Plus)タイヤ
ここまでキレイに使い切ったタイヤ、久しぶりに拝見しました。

表面のゴムがきれいに一皮むけてキャンバスが出ています。
ちょっと顔を覗かした布が突き刺しパンクに強いとされる繊維。通常のタイヤだとここまで使う前に布が裂けてしまうことが多いんです。さすが耐パンクタイヤ。
一番多いパンクの原因って、お使いになる自転車のタイヤの空気圧が足りなくて、チューブをもんでしまったり道路の段差に乗り上げてチューブが切れるショック切れかと思います。

ここまできれいに使い切るのって表彰ものですね。
パンクするのは空気が入っているからだ!という理論に基づいて潔く最初からゴムの塊を入れてしまうノーパンクタイヤもありますが、乗り心地がよくありません。

そうそう、言いたかったのは耐パンクタイヤはノーパンクタイヤより軽くて丈夫ということと、空気をちゃんと入れて走れば大半のパンクは防げますということでした。
特に見知らぬ出先でパンクした時は途方に暮れてしまいますね。
パンクの原因は様々ありますがその中で突き刺しパンクに強い
ブリヂストンの上位モデルの通学車に装備されているプラス(Plus)タイヤ
ここまでキレイに使い切ったタイヤ、久しぶりに拝見しました。
表面のゴムがきれいに一皮むけてキャンバスが出ています。
ちょっと顔を覗かした布が突き刺しパンクに強いとされる繊維。通常のタイヤだとここまで使う前に布が裂けてしまうことが多いんです。さすが耐パンクタイヤ。
一番多いパンクの原因って、お使いになる自転車のタイヤの空気圧が足りなくて、チューブをもんでしまったり道路の段差に乗り上げてチューブが切れるショック切れかと思います。
ここまできれいに使い切るのって表彰ものですね。
パンクするのは空気が入っているからだ!という理論に基づいて潔く最初からゴムの塊を入れてしまうノーパンクタイヤもありますが、乗り心地がよくありません。
そうそう、言いたかったのは耐パンクタイヤはノーパンクタイヤより軽くて丈夫ということと、空気をちゃんと入れて走れば大半のパンクは防げますということでした。
タグ :タフロード プラスタイヤ
2015年06月09日
サイクルコンピューターの補正
先日のサイクルコンピュータの距離表示がより正確になるように調整をしてみました。

セットアップの際に、速度や距離表示の基準になるタイヤの周長(一回転で進む距離)を取扱説明書にある数字を元にセットするんですが、実際の数字と違うことが多いんです。
ワタクシの自転車は26×1.25なのでこの表で示す数字は 「195」
一回転で195Cm進むということです。

ところが実際に測定してみると・・・
まずタイヤの一箇所に印をつけて引き出して床に敷いた巻尺のスタート地点にピッタリとあわせます。

で、巻尺に沿って真っ直ぐに進めていきます、慎重に。

タイヤが一回転したらその部分の目盛りを読みます。ワタクシの自転車は196.2?位ですね。一回の測定では信憑性が無いので数回測って平均を取ります。今回は196Cmにしましょう。

この数字をセットアップの際に入力すればOKです。サイクルコンピューターの機種によっては詳細設定が出来ないものもあります。説明書をご確認くださいね。
セットアップの際に、速度や距離表示の基準になるタイヤの周長(一回転で進む距離)を取扱説明書にある数字を元にセットするんですが、実際の数字と違うことが多いんです。
ワタクシの自転車は26×1.25なのでこの表で示す数字は 「195」
一回転で195Cm進むということです。
ところが実際に測定してみると・・・
まずタイヤの一箇所に印をつけて引き出して床に敷いた巻尺のスタート地点にピッタリとあわせます。
で、巻尺に沿って真っ直ぐに進めていきます、慎重に。
タイヤが一回転したらその部分の目盛りを読みます。ワタクシの自転車は196.2?位ですね。一回の測定では信憑性が無いので数回測って平均を取ります。今回は196Cmにしましょう。
この数字をセットアップの際に入力すればOKです。サイクルコンピューターの機種によっては詳細設定が出来ないものもあります。説明書をご確認くださいね。
タグ :サイクルコンピューター設定
2015年03月07日
耳切りばさみ
最近めったに使用しなくなった工具です。
でもこれが無いと出来ないタイヤの修理があるんです。

うんと昔の駅員さんが、改札でカチャカチャ鳴らしながら切符に切込みを入れていたハサミと形が似ていますね。

専門的な話は割愛して・・・昔の自転車のタイヤは耳式(BEタイヤ)といってタイヤ全体でチューブを包み込むタイプのものでした。そのタイヤにチューブを入れる切込みを入れるためのハサミです。

こんな感じに切れます。

タイヤを取り付けるためのリムの形も違いますね。リヤカーのタイヤもこの方式です。結構コツと力が必要なタイヤ交換です。

でもこれが無いと出来ないタイヤの修理があるんです。
うんと昔の駅員さんが、改札でカチャカチャ鳴らしながら切符に切込みを入れていたハサミと形が似ていますね。
専門的な話は割愛して・・・昔の自転車のタイヤは耳式(BEタイヤ)といってタイヤ全体でチューブを包み込むタイプのものでした。そのタイヤにチューブを入れる切込みを入れるためのハサミです。
こんな感じに切れます。
タイヤを取り付けるためのリムの形も違いますね。リヤカーのタイヤもこの方式です。結構コツと力が必要なタイヤ交換です。
タグ :BEタイヤ
2015年02月17日
フレームの曲がり
転倒したり事故にあった自転車の車体が曲がっている場合があります。
曲がり具合を判断する方法のひとつの紹介です。
自転車のフレームのヘッドを中心にして左右に糸を張ります。

ヘッドにまわした糸をフレーム後方にある左右のエンドまで引っ張って貼り付けます。

反対側も同じ位置に貼り付けるのがポイントです。

フレームヘッドを頂点とした二等辺三角形が出来ます、この中央にあるシートチューブ(サドルを取り付ける縦のパイプ)と左右の糸の間隔を測定するわけです。まず左側・・・3.5mm

今度は右側・・・3・1mm わずかですが曲がっています。数ミリ違うだけですが、前輪と後輪の位置がずれているのでまっすぐ走れません。クランク側のギアと後輪のギアを結ぶチェーンラインがずれているのでチェーンから異音も出て外れやすくなります。

その昔は、フレーム修正をしたのですが現在は安全を考えて交換をおススメしています。
曲がり具合を判断する方法のひとつの紹介です。
自転車のフレームのヘッドを中心にして左右に糸を張ります。
ヘッドにまわした糸をフレーム後方にある左右のエンドまで引っ張って貼り付けます。
反対側も同じ位置に貼り付けるのがポイントです。
フレームヘッドを頂点とした二等辺三角形が出来ます、この中央にあるシートチューブ(サドルを取り付ける縦のパイプ)と左右の糸の間隔を測定するわけです。まず左側・・・3.5mm
今度は右側・・・3・1mm わずかですが曲がっています。数ミリ違うだけですが、前輪と後輪の位置がずれているのでまっすぐ走れません。クランク側のギアと後輪のギアを結ぶチェーンラインがずれているのでチェーンから異音も出て外れやすくなります。
その昔は、フレーム修正をしたのですが現在は安全を考えて交換をおススメしています。
タグ :フレーム修正
2015年02月08日
ノーパンクタイヤの修理
時折、広告などで見かけるパンクしないタイヤ「ノーパンクタイヤ」
自転車やバイクに乗るときパンクって嫌ですよね。そんな悩みから開放してくれる夢のような存在・・・
そのタイヤが修理(交換)に入ってきたのでどんなタイヤかご紹介します。
よく見ると空気を入れるバルブがありませんね^^
かなりピッチリはまっているので バイスプライヤーを改造した専用工具で隙間を作りタイヤレバーを差し込んで リムからタイヤをはずしていきます。

中からゴムで出来たチューブが出てきます。空気の代わりにゴムが詰まっているので重いです。

硬くて乗り心地がよくないので、物によっては「発砲ゴム」を使ってクッション性を持たせたものもありましたが、しばらく使用しているとゴムの中の気泡がつぶれてしまい、非常に重くなるのが難点です。このタイプは全部ゴム製でした。

組み付けは、先ほどの逆の手順で少しずつレバーではめていき 完成です。

パンクしないメリットがあるのですが、実際にあまり普及が進まないのは、乗り心地がよくないのとコストが高めだからですね。
乗り心地は空気の入ったタイヤが一番!パンク予防のために適正な空気圧で快適に走行しましょう~♪
自転車やバイクに乗るときパンクって嫌ですよね。そんな悩みから開放してくれる夢のような存在・・・
そのタイヤが修理(交換)に入ってきたのでどんなタイヤかご紹介します。
よく見ると空気を入れるバルブがありませんね^^
かなりピッチリはまっているので バイスプライヤーを改造した専用工具で隙間を作りタイヤレバーを差し込んで リムからタイヤをはずしていきます。
中からゴムで出来たチューブが出てきます。空気の代わりにゴムが詰まっているので重いです。
硬くて乗り心地がよくないので、物によっては「発砲ゴム」を使ってクッション性を持たせたものもありましたが、しばらく使用しているとゴムの中の気泡がつぶれてしまい、非常に重くなるのが難点です。このタイプは全部ゴム製でした。
組み付けは、先ほどの逆の手順で少しずつレバーではめていき 完成です。
パンクしないメリットがあるのですが、実際にあまり普及が進まないのは、乗り心地がよくないのとコストが高めだからですね。
乗り心地は空気の入ったタイヤが一番!パンク予防のために適正な空気圧で快適に走行しましょう~♪
タグ :ノーパンクタイヤ